【海外書籍】ダ・ヴィンチ・ノート【ダイジェスト全文掲載】
サンプル(全文掲載)
2019.06.10
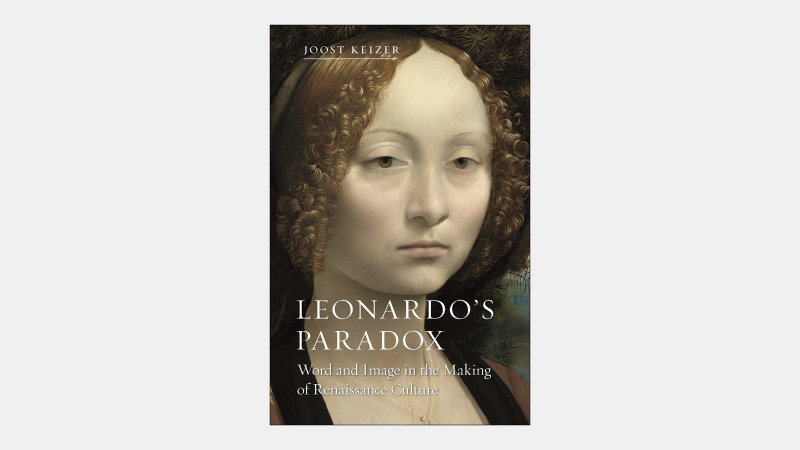
原題:Leonardo’s Paradox | Joost Keizer 著 | Reaktion Books | 208p
1.ダ・ヴィンチのノートを見る
2.自然の残した痕跡
3.創作
4.時間
ルネサンス期の巨匠、レオナルド・ダ・ヴィンチ(1452-1519)の名を知らない人は稀だろう。
2019年は、ダ・ヴィンチ没後500年にあたり、欧州を中心にその類まれなる才能や、残された謎について再検証する気運が高まっているようだ。
その「謎」の一つに、彼が書き記した多数の「ノート」がある。
本書では、美術、音楽、建築の他、天文学や物理学、動植物学など自然科学分野でも偉大な足跡を残したレオナルド・ダ・ヴィンチの芸術作品ではなく、日常的に書き記していた「ノート」に着目。
一見解読不能とも思える略語や暗号、「鏡文字」などに満ちあふれたノートの中身から、「文字」と「絵(イメージ)」の関係性、「世界語」としての「絵」の可能性といった、天才ならではの本質的かつ先見的な思考の断片を浮かび上がらせている。
著者はオランダのフローニンゲン大学の美術史准教授。ルネサンス美術とバロック美術を専門に研究し、『僕はダ・ヴィンチ(芸術家たちの素顔)』(パイインターナショナル)など、ミケランジェロ、ダ・ヴィンチ、デューラー他に関する多数の著書がある。
ダ・ヴィンチ独自の略語、暗号、鏡文字で書き記された「ノート」
レオナルド・ダ・ヴィンチは、公証人を父に、1452年に生まれた。非嫡出子だったこともあり、父親の家で育ったものの家業は継がなかった。しかし、ペンで紙に文字を書き記す公証人の仕事を幼い頃から見ていたため、「手書き文字」に強い愛着を感じるようになったようだ。
ダ・ヴィンチのものとされるノートが多数残されている。現存するだけで22冊、あと少なくとも10冊は存在すると言われている。いずれにも、膨大な「手書き文字」が書き連ねられている。何歳ごろからかは定かではないが、ダ・ヴィンチには、日常的にノートに文字を書き記す習慣があったとされている。
彼は、さまざまなサイズのノートを使い分けていたという。22冊の中には、詳細な図面や長い文章を記した大きなノートもあれば、外出の際に常にポケットに入れて持ち歩いていたと思われるメモ帳のようなノートもある。これらのノートは、思考の整理や、見たり聞いたり、読んだりした物事の記録などに使われ、後日に記憶を取り戻す際にも役立っていたようだ。
このようなノートの取り方は、現代の私たちからすれば、普通に感じられるかもしれない。だが、ノートに書かれた「文字」や「言葉」を見れば、決して普通ではないことがわかるだろう。まず、オリジナルの略語や、彼が独自に編み出したと思われる暗号が多用されている。それから「鏡文字」も見られる。これは、鏡に映ったように左右が逆転した文字で、ダ・ヴィンチの場合、左手で「右から左へ」書かれている(※ダ・ヴィンチは左利きだったとも、両利きだったとも言われている)。すなわち、ダ・ヴィンチがノートに書き記した文字は、同時代のミケランジェロらに比べても、群を抜いて読みづらいのだ。
文字だけでなく、内容も一見では他者に理解できないものだ。1冊のノートに多種多様な内容が、思いつくままに雑多に記されてもいる。削除や訂正も多い。ダ・ヴィンチが「自分のため」だけの目的でノートを使っていたのは間違いないだろう。彼の存命中、これらのノートの中身を知っている者はほとんどいなかった。
ダ・ヴィンチの死後、残されたノートを見つけた人々は、交友関係や人生観、政治信条、一目置いている他の画家についてなど、彼の人となりや思考・哲学などがわかるのではないかと期待した。だが、そうしたものはほとんど見つけられず、大いに失望したそうだ。
知識の変化を「固定化」する印刷よりも「手書き文字」にこだわる
グーテンベルクが活版印刷技術を発明したのは15世紀半ば。ダ・ヴィンチが活躍する頃には、イタリアにも印刷機が普及していた。印刷された書籍もヨーロッパの各都市で、相当数出回っていたはずだ。そんな中でも、ダ・ヴィンチは「手書き」にこだわっていたという。自身の書いたものを活字にして印刷、出版することにまったく興味を示さなかった。
その理由の一つは、知識や情報の「固定化」を嫌ったことにあると言われる。ダ・ヴィンチにとって「書く」という行為は「真実」に近づくためのプロセスだった。「真実」とは常に変わっていくものだ。少なくとも彼はそう考えていた。したがって、印刷して一冊の本にしてしまえば、真実の変化に対応できないというのである。
ダ・ヴィンチがノートに文字を「書く」時、書かれた内容は「確定」ではない。絶えず見直す対象となる。見直して修正したり、新しい真実を書き加えたりする場合でも、元の文字を塗りつぶして見えなくすることはない。必ず(自分が)読める状態に残しておく。また考えが変わって、修正前の意見に戻ったりすることもあるからだ。
また彼は、活字や印刷は、文字の「個性」を殺してしまうことを恐れたとされる。手書き文字は人によって千差万別であり、書いた人それぞれの個性が表れる。また、書いた主体の身体性と結びつく。たとえば文字の震えの原因は、一時的な身体の疲れかもしれないし、年齢による気力の衰えかもしれない。だが、当時の活版印刷では、そうした個性を表現するのは不可能であり、「文字の個性」は排除される運命にある。
とりわけ、ダ・ヴィンチのノートに書かれた文字は、前述の鏡文字に代表される、きわめて個性的なものだ。彼は、凝った飾り文字や繊細な細い文字、うねった線など、手書き文字の「見た目」にこだわっていた。ノートには、文字以外に複雑な図面やスケッチなどが描かれているのだが、それらも、「個性的な文字」も、当時の印刷技術では再現不可能だった。
ダ・ヴィンチは、印刷そのものを毛嫌いしていたわけではない。むしろ印刷技術には可能性を見出していた。そうした文字飾りや図面をも印刷できる技術を発明しようとしていたが、その努力はかなわなかったのだ。自分の書いたものの出版に興味を示さなかったのは、当時の印刷技術の限界に不満を抱いていたのも一因なのだろう。
「読む」という無意識のプロセスを分解する「ダ・ヴィンチのノート」
私たちは、読みやすい書体で印刷されていたり、クセがひどくない手書きの文章を読む際に、一つひとつの文字を意識することはほとんどない(※アルファベットのような表音文字の場合)。個々の文字に意味はなく、単語や文章になって初めて意味をなすからだ。
ところが、ダ・ヴィンチのノートを開くと、最初に目に飛び込んでくるのは文章ではなく「文字」だ。そして、読もうとしても、略語や暗号や鏡文字が邪魔をして、何が書いてあるか判然としない。一つひとつの文字を注視し、略語に慣れたり、鏡を使ったりすることで、ようやく「文章」として読めるようになる。ダ・ヴィンチのノートは、私たちが当たり前に行っている「読む」という無意識のプロセスを分解し、「文字」の存在を否応なく意識させるのだ。
未知の外国語で書かれた文章を目にしたケースを思い浮かべてみよう。読めなければ、その文章から得られる情報は、文字の「見た目」しかない。その「見た目」を注視することで、文字そのものの美しさや特徴に気づいたりもする。実際、ダ・ヴィンチや、彼と同時代の画家たちは、アラビア語やアジアの言語の文字の美しさに惹かれ、しばしば作品に取り入れている。
「文字」と「絵」の関係に「世界語」の可能性を見出す
ダ・ヴィンチは、世界中で争いが絶えないのは、人類が国家や民族ごとに異なる言語を使っているからだと考えた。そこで「世界語(universal language)」があれば、人同士のつながりが強化され、争いが少なくなるのではないか、といった内容をノートに記している。そして「絵」が、その世界語の役割を果たせると信じていたようだ。「絵」であれば、言葉が通じない同士でも、情報や知識の伝達や、感情の共有が可能だ。
さらに彼は、文字と絵は「線を引く」行為という点で共通しており、書き言葉のルーツは「絵」ではないか、とも指摘している。その際、ダ・ヴィンチの念頭にあったのは、その頃に欧州で盛んに研究されていたエジプトの象形文字(ヒエログリフ)だったと推察できる。ヒエログリフは、話し言葉を介さない、純粋な書き言葉であったとされる。つまり、話し言葉を記録するために文字にしたのではなく、あるモノを表現して記録し、伝達するため、話し言葉にする以前に、ヒエログリフが作られたのだ。
ダ・ヴィンチは、ヒエログリフと同様、絵画も話し言葉を介さずに世界をダイレクトに表せる手段であり、そこに「世界語」の可能性を見出した。話し言葉には、どうしても地域や民族による違いが出てしまうからだ。ダ・ヴィンチはヒエログリフを彷彿とさせる絵文字や判じ絵も、ノートに多数残しているが、おそらくそれらは「世界語」に向けての試行の一部だったに違いない。
コメント
本文にある、ダ・ヴィンチが活躍していた当時の印刷技術の限界は、現代ではいずれもクリアされている。知識や情報の「固定化」については、いつでも更新できるウェブサイトでは起こり得ない。「個性的な文字」に関しても、印刷技術の進歩、さらにはHTMLで簡単に再現できるようになった。ついでに言えば「世界語」についてもYouTubeやインスタグラムの動画や画像で実現しつつあるのではなかろうか。だが、これだけ自由な表現が可能になった現代でも、ダ・ヴィンチほどの天才は登場していないように思える。ある程度の「不自由さ」が、物事の本質を見きわめる才能に必要なのかもしれない。
※本ダイジェストは著作権者からの許諾に基づき、書籍本文を再構成して作成しています。
※本ダイジェストをユーザーご自身でのご利用以外で許可なく複製、転載、配布、掲載、二次利用等行うことはお断りしております。